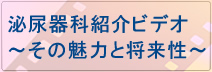教授挨拶
山口大学大学院医学系研究科泌尿器科学講座のホームページをご覧頂き、ありがとうございます。当講座を主宰させていただいている白石晃司と申します。教授就任3年に際し、感じていることを申し上げ、あらためて当科の紹介をさせていただきます。
まず感謝!!
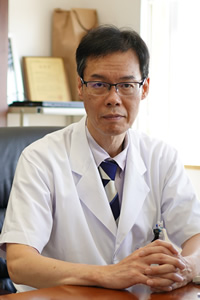 多くの患者さんに受診していただき、私たちの経験値を上げることは臨床医にとっては必須です。かつ医療事故を起こさず、病院経営に貢献し、基礎および臨床研究を推進することは大学病院においては普通のことのようで、そのためには並大抵の努力では達成しえないことを痛感しています。
多くの患者さんに受診していただき、私たちの経験値を上げることは臨床医にとっては必須です。かつ医療事故を起こさず、病院経営に貢献し、基礎および臨床研究を推進することは大学病院においては普通のことのようで、そのためには並大抵の努力では達成しえないことを痛感しています。
私たちは年間800件程度の手術を担当し、大学病院での入院待ち時間を考慮し、近隣の施設にて私たちが出向して行う手術(不妊症やシャント関連など)も含めれば、年間1000件以上という全国の大学病院の中でもトップクラスの症例数の手術を、少数の医局員でこなしています。
まずはじめに、県内外を問わず山口大学泌尿器科を受診していただいた患者さまに感謝、そしてその診療を支えてくれている研修医からスタッフの先生、関連病院の先生方、そして病院関係者の方々に深く感謝申し上げます。感謝の気持ちを胸に臨床、研究および大学病院としての大切な使命である教育に、これからも邁進していく所存でございます。
地域医療の要として貢献する
大学病院での泌尿器科では癌診療が主で、当然私たちが最も力を入れている分野でございます。新薬など数多くの治験も実施しております。
多くの施設が乱立している都市部の大学病院であれば、特定の強みのある診療で成り立ちますが、山口においては地域医療の要として、オールラウンドな診療が求められます。腎生検からステロイドパルス、血液透析、腹膜透析、そして腎移植、男性不妊症、尿道下裂などを含む小児泌尿器科など多くの大学病院泌尿器科ではなかなか手が出せない領域にも注力し診療を行っています。「オールラウンドな泌尿器科診療」は私の就任時から目標の1つとして掲げてきたものであります。やるからには質の高い世界一の診療を目指そうと医局員を鼓舞し、これからも愚直に努力していきたいと思います。
泌尿器科の診療範囲は非常に広いです。行き場を失った患者さんも数多く山口大学泌尿器科を受診されています。その結果、最近手術件数として増加しているものに、骨盤臓器脱に対するロボット支援下仙骨膣固定術や尿道外傷等による尿道形成術、未だ病態が不明の慢性陰嚢痛などのケースが増加しています。一方で、2023年度は泌尿器科の最もメジャーな手術であるロボット支援下前立腺全摘は全国国立大学において2番目に多い症例数(120例強)を経験しています。現代の癌治療は「生きれて良し」ではなく、「いかに生きるか」が、つまり生活の質(QOL)の改善・維持が重視されています。局所前立腺癌は治って当たり前です。手術後の排尿や性機能の悩みについても傾聴し、研究し、患者さんにフィードバックするという私たちのスタンスが患者さんたちにも伝わり、当院を選んでいただいているのではないかと思います。ここでもあらためて感謝申し上げます。
生活の質(quality of life: QOL)を追求した癌診療
腎癌、膀胱癌および前立腺癌においてロボット支援手術は、もはや最新のものではなく、山口大学泌尿器科におきましてもロボット支援前立腺全摘除術開始から1000件を超えました。小さな傷で癌を完全に取り除くことは当然のことですが、術後の勃起、排尿および腎機能障害や不妊、治療への満足度や経済性についての研究は日本においては非常に遅れています。高いQOLの追究が次世代の癌治療に求められてます。低侵襲手術とは手術の方法ではなく、患者さんがいかに早く合併症なく退院でき、高いQOLを維持できるか、ということと考えております。時には鏡視下手術より開腹手術のほうが患者さまにとってメリットが大きいことも多々あります。
手術以外にも、さまざまな癌に対する免疫チェックポイント阻害剤、抗体薬物複合体などを中心とした、臨床治験を多く行っており、最新の治療を常に提供できる体制を構築しています。
原発性アルドステロン症、クッシング症候群および褐色細胞腫などに対する鏡視下手術を、多科診療連携のチーム医療にて積極的に行っています。
慢性腎臓病に対するトータルな対応
山口大学には腎臓内科が独立した診療科として存在しないため、循環器内科および小児科の先生方と協力しながら腎臓病に立ち向かっています。泌尿器科は蛋白尿の診断から、腎生検、ステロイドや免疫抑制剤を用いた腎炎の治療、そして慢性腎不全に至った場合の腎代替療法として血液透析、腹膜透析および腎移植まで慢性腎臓病に対するすべてのフェーズを担当しています。腎移植件数は年間約20〜25例と、中国四国地方においては多くの件数を行っています。
男性不妊症:アジアそして世界の中心として
精巣内で精子を作れない非閉塞性無精子症に対し、顕微鏡下精巣内精子採取術(micro-TESE)を2001年に西日本で初めて施行しました。しかしmicro-TESEを行っても約70%の患者さまからは精子採取できず、不妊治療の終わりを告げなければなりません。私たちは2012年に新たな内分泌療法を開発し、2回目のmicro-TESEにおいて世界で初めて精子採取が可能であったことを報告し、非閉塞性無精子症治療におけるブレークスルーとなりました。国内外から多くの患者さまが受診され、全世界の患者さまから多くの喜びのご報告をいただいております。新たな内分泌療法の研究も行っています。そのほかにも精索静脈瘤や閉塞性無精子症などにおいて山口大学発の多くの新規術式の報告を行っています。2022年4月から不妊治療に保険適用が開始されました。多くの患者さまに受診していただけるよう、私たちも万全の体制を敷いております。
LOH症候群やペロニー病などの性機能障害の診療や研究にも力を入れています。
毎年のように国内のみならず海外、とくにアジア圏の泌尿器科の先生からの研修の要請があり、受け入れております。
小児泌尿器科:誰がやるの?私たちでしょう!
やさしさと繊細さが要求される小児泌尿器科手術。ロボットや腹腔鏡などを用いた癌の手術とは異次元の技術が要求されます。その結果、多くの大学病院や総合病院において、小児泌尿器科診療は敬遠され、小児症例は都市部のこども専門病院に集中する傾向があります。中国四国地方にはこども病院が存在しないことと、私たちは尿道下裂や水腎症、膀胱尿管逆流症などの手術を得意としていることで、泌尿器科外来は小さな子供たちでいっぱいです。私たちのモットーは小児期だけの治療に終始せず、特に性腺疾患などはきちんと成人まで責任をもって継続的に小児泌尿器科診療を行うことです。移行期医療(transition medicine)とも言われます。小児性腺疾患を思春期(第2次性徴)、成人期(不妊症や性機能障害)、中高年期(男性更年期)まで一連の病態として理解するために、私の造語ではございますが、”Pediatric Andrology”という概念を提唱しています。
研究
私は就任時に、「私たちが日頃、患者さまに行った治療をデータ化し客観的に見直し、学会発表や論文により公表し、批判を仰ぎ受容することで、自分たちの特徴や弱点、そして新たな発見があり、次の活路が見出されます。」と述べました。しかし、業務過多、コンプライアンスの変化、働き方改革、ダイバーシティーなども相まって、医局員すべてに一律に当てはめるわけにはいきません。
しかし、成果(論文や学会発表の有無)がどうであれ、「臨床医は皆physician-scientistであるべきで、臨床現場から生じた疑問点を探求する姿勢は、患者さまを診療するのであれば、一生持ち続けるべき態度である」というポリシーは曲げずに貫きます。あえて目標を言葉にするなら、“Scientist-like physician”を目指そう、といたします。「あの先生手術すごく上手で臨床だけと思っていたけど、考え方は結構scientificだよね」と自分ではなく他人から言われるような泌尿器科医が育つことを願います。私自身もそのように言われてみたいですが、今まで一度もございません。
最後に
私は副病院長(医療安全担当)として、院内のすべてのインシデントを目の当たりにし、医療の怖さを毎日実感しております。一方で、「泌尿器科は雰囲気や風通しが良い」などの感想を、ほぼすべての臨床実習を回った学生からいただいております。先輩後輩、男女を問わず自由で建設的な意見が言える雰囲気は、チーム医療を行い、安全に高度な医療を患者さんに提供するための必要最低条件と考えます。ここでも医局員全員に感謝です。
忙しいけれども働き甲斐のある、テストステロン(女性も!)に満ち、誰もが常にはつらつとしている泌尿器科医局を目指します。